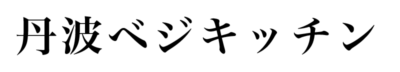随筆【漆胡樽 ー正倉院展にそえてー】


洛陽 龍門石窟
O先生、会いに行きます
平安遷都1300年
毎年、待ちわびる奈良国立博物館特別展がまもなく始まる。パソコンで検索してみると、今年は平安遷都1300年の記念の年ということで、代表する宝物と併せて、平城京に生きた人々の生活が伺える御物も展示されると解説されていた。
『あった!』。私が焦がれ、待ち続けた御物が永い眠りから覚醒されついに私の前に現れるのだ。この事を知ってから、心の中で海が大きくうねりざわざわと波立っている。

シルクロードの必需品
井上靖の詩集「北国」に「漆胡樽」という詩がある。漆胡樽とは、中央アジアの砂漠を行く隊商の駱駝達の背に、水を湛えて運ばれた水運搬用の道具のことである。この生活道具が、いかなる事情か駱駝の背を離れて東方一小国の王室に辿りつき、そのままこの国の宝物として二千年余の眠りについた。
敗戦直後、秋の日差しの中で長い時を経てついに宝倉の扉が開いたのだ。筆者井上靖は一新聞記者の立場でこの機会に遭遇する。
『この第一回正倉院展で展示された華麗な財宝のいずれにも増して、生活道具である漆胡樽は敗戦国の人々に心の安らぎを与えた』と、筆者は詩と同タイトルの短編にも書いている。
O教授のこと
私は幼い頃から本の虫であった。国文学よりも海外文学が好きで図書館の全集を読み尽くすような少女であった。その私に近代国文学の面白さ、とりわけ井上靖の魅力に目覚めさせてくれたのが、O教授だった。当時O先生は40代だったと記憶するが、その面差しや話し方、生き方が当時の私にはとても素敵に映り憧れの存在だった。
O先生は講義をするというよりも、独り言のように何となく語るという感じで終始した。まるで自分の考察の確認のために“話し言葉”にしてみる・・といったような感じだった。学生の方を見てはいるが、実のところ心は作品やその作者の中に入り込んでいて、私たちがどうあろうが関係なしというような感じであった。しかし、決していい加減な講義ではなかった。このことはO先生の名誉のためにも記しておかねばならない。
O先生のファンは私だけではなかった。
今頃の季節だったらたぶんそう、とても品の良い茶色の縞のウールジャケットを着ていたことを昨日のことのように思い出す。ジャケットには同色系のスエードの肘あてがしてあって私はそれが好きだった。それを教壇脇の椅子の背に無駄の無い動作で掛けてから、ワイシャツの袖ボタンをゆっくりと外す。その袖部分を丁寧に2段くらいゆっくりと折り曲げチョークで汚れないように配慮していた。
その講義は未熟な若い私たちが気付かない、しかし小さくてもチカッと瞬く真実や、登場人物らの詳細な感情にハッと気付かせてくれる講義だった。先生は遠くを見ながら一人で思い出すように『ふっ』と笑ったり、また時に苦しそうな表情で解説した。それは満足感のある密度の濃い時間だった。
続きの会話を始めたような雰囲気で、なんとなく自然に講義が始まる様子は、他の先生方とは一風変わった始まり方であったが、私たちはそれを歓迎していた。その一連の儀式のような動作も私たちは好きだったし、いつもちょっぴり緊張して居ずまいを正しながらその動作を目で追い、確かめたものだ。この数分間は私たちには必要な時間であった。「さあ、始まるぞ」という気合が徐々に満ちて、教室内にシンと清涼なる気が流れた。
私はそこがまるで私の指定席のような感じで、いつも前の席に陣取り、O先生の顔から一瞬たりとも、目を逸らしたくない、まばたきもしたくないほどの気持ちで熱心に講義を筆記したものだった。
O先生は私たちが新入生の年、講義の資料に井上靖の詩集「北国」を取り上げた。この詩集をエッセンスにして詩と同タイトルの小説を筆者は沢山発表している。その詩集の一篇一篇を丁寧に解釈し鑑賞したこの時間が無性に懐かしい。真剣に学んでいた当時の私たちがとてもいじらしく思える。90分があっという間であったことを覚えている。
指切げんまん
幸せな学生時代は瞬く間に終わり、公立図書館へ司書として勤務した。完成してまだ半年の真新しい図書館で司書として勤務し、仕事の困難さと充実感を味わった。結婚、出産を体験しながら、人間関係の難しさなど人並みの経験を積んだ頃、O先生と副学長の U先生から嬉しいお誘いが掛けられた。
大学が海外の学校と姉妹提携を結ぶために、中国洛陽の外国語学院へ視察に行くことになったのだ。その同行者として二人の先生の共通の教え子であり、司書として勤務している私を含めた三人に白羽の矢がたったのだ。
井上靖の作品を夢にまで見た憧れの中国である。しかもあのO先生と同行なんて、こんなラッキーなことは人生にそうあることではなかった。
そしてもう一つ、私が中国に固執するには訳がある。父が満州からの引き上げ者であったことだ。父は大陸育ちの影響だろう、大らかで優しい人だった。少年期を中国で過ごした父は、中国には日本には生息していない大きな川魚がいて、それを中国の友達と釣って遊んだことや、蓮畑に入って泥だらけの大きな蓮を掘り、土のついたまま焚き火で焼いて食べたことなどを、私が幼い頃懐かしげに話したものだった。その度に私の想像は大きく膨らんで、「いつかお父さんと一緒に中国に行く!」と指切りげんまんして誓っていた。
だが、その父はもう居ない。

赤い月光をたよりに
15年ほど前の中国は、現在とは雰囲気がまるで違った。何より当時はまだ緑色の人民服が街の中に溢れていたし、北京とその郊外ではこれが同じ国なのかと思うほどに、風景やそこに住む人々の様子には大きな落差を感じた。
旅の前半は中国の国会図書館である北京図書館、北京大学、北京大学図書館の視察、旅の後半は姉妹提携をする予定である洛陽にある外国語学院での視察と講演、協議だった。
北京から洛陽へ向かう夜行列車でのこと。
時々、キキーッと大きな音を出して止まる列車は、実にのんびりと走行する。外は徐々に薄暗くなり、見晴るかすコーリャン畑が続いているかと思えばチカチカと遠くに光が見えて小さな村があることを想像させた。ひょろ長く背の高い街路樹の黒い陰が、切れることなく遥かに続いていた。その長さといったら想像を超えた長さで、しみじみと“大陸”を実感した。線路から200メートルほど離れてその街路樹の続く道があり、ほぼ平行に線路が走っているらしかった。時々、小さな明かりを頼りに馬車、いや、もしかしたら驢馬や騾馬かもしれないが、その曳いてる動物の姿が見えないほどの大山の荷物を積んで運んでいる様子が私には驚きで、それらを追い越す度にその姿が闇の中に見えなくなるまで窓に顔をくっつけて後ろをみたものだ。
その荷物の中に、道端に、そこかしこに小さな男の子だった父がニコニコと笑いながら私を見ているような気がしてならなかったのだ。大陸の匂いや空気感を身体いっぱいに感じた。父はこんな風景の中で育ったのだろうかなどと想像した。優しかった父に無性に会いたかった。
気が付くと前方に真っ赤な丸い月が出ていた。黄砂の影響だろう。始めてみた大陸の月はどきりとするほどの存在感で私を圧倒した。鮮血が滴るかのような恐ろしい月だった。
井上靖の作品『漆胡樽』の舞台であったあの時代にも、こんな赤い月光を頼りに駱駝の隊商は進んだのだろうか、一抱えもある一対の“黒漆角型”の樽を積んで。
棘
一昨年、O先生の訃報をU先生からの連絡で知った。その時から、中国での出来事が心の中で繰り返えし思い出され、その度に心の傷が疼く。
旅の途中、O先生は悲痛な顔で私にご自身のことをこう評した。『私は、文学のこと意外はまるで知らない常識のない人間なのです。現在の人間社会の中では不器用にしか生きられない、恥ずかしい人です・・』と。そのとき先生は何に支配されていたのだろう。あの言葉は大陸の強い酒に言わせられたのかも知れない。
その時先生にどんな顔を向けたのか、どのように言葉を繋いだのか。私は思い出せない。もしかしたら、先生の言葉に戸惑って、まったく的外れな言葉で誤魔化したのか・・笑ってすましたのか。それとも全く話せなかったのかもしれない。ああ・・もう、あの時へは戻れない。未熟者の私がせめてあの瞬間は無言であったことを、今は願うばかりだ。
父のように尊愛していたO先生の意外な言葉に、私はきっと慌ててしまい、的確な言葉を発してはいない。今から想像すれば容易に分かることだが、教え子の私からお利口さんな言葉を望んではいなかった。きっといつものように、なんとなく自分が考えていたことを言葉にしてみただけだったのだろう。きっとそうだろう。私の反応などは最初から関係なかったに違いない。
でも私は自分が許せない。私なりの言葉で先生の心をやさしく包んであげられるような言葉が言いたかった・・・。齢を重ねこのことに気が付いた私は、この時から心に棘が刺さったままだ。

黒漆角方 漆胡樽
漆胡樽に会いに
今回の特別展が、おそらく私が存命でいる間の「漆胡樽」に会える最初で最後の機会であろうと推測している。痛んだ心の棘を抜くのは多分今年しかない。 “黒漆角型”の「漆胡樽」を先生の身代わりにして、あの時中国で言えなかった言葉をはっきりとお伝えしようと思っている。
『O先生、私は先生のお陰で今も本の虫です。先生が蒔いてくださった種から、私は大いなる収獲を得ています。文学から学んだ人生の機微は現世でも“非常識”ではありませんでした。今世の数年間、O先生から御教授を賜ったことは私に幸運をもたらしています。生身の私たちは正倉院の御物のように永遠に存在はできませんが、先生の残された研究成果や詩、私たちへのご教示は残ることでしょう。来世、出来ることなら、ぜひこの漆胡樽の前でお会いしませんか。それまでこの一対の樽に、私の思いを静かに注いで、眠らせておきますから。だから・・指きりげんまん!です。』
完